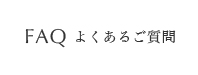着付講師 原清華先生と巡る♪西陣織ツアー 工房見学会の御案内🌈
2022.10.06

大人気 着付講師 原清華先生による
「西陣織 工房見学ツアー」を開催いたします。
【イベント】11月11日 産地を読み解く勉強会〜西陣織工房見学編|着物と和のイベントはこにわ公式サイト (hakoniwa-japan.com)

リユース着物目利き講座で話題の着付け講師
原清華先生と西陣織の産地を巡る見学&勉強会。
カジュアルからフォーマルまで、
着物ファン信頼の巨大産地 西陣の歴史と最先端の製造現場でその技術を学ぶ会を開催します。

あらゆるニーズに応える織物の宝庫西陣
さて今回皆さまをお連れする先は、京都西陣。
その起源は平安京の時代までさかのぼると言われ、
日本の数ある織物産地の中でも生産量の多さと歴史の深さゆえに、
作っている着物や帯のバリエーションが非常に豊かなワンアンドオンリーの産地です。
カジュアルからフォーマルまで幅広く、またお値段も驚くような
高級品から驚くようなお値打ち優良品まで、とにかく振れ幅が広い。
西陣織がフォーマルの袋帯のイメージだった方は
まずここで目からウロコ、となるでしょう。
アクセス良好な街中の産地
西陣エリアはアクセスの良さも魅力。
地下鉄やJRなどの最寄り駅はございませんが、
京都駅など主要の駅からバスやタクシーで容易にお越しいただくことが出来ます。
通りを歩けば、織元と呼ばれるメーカーはもちろん、
糸屋さん、染屋さん、整経屋さんといった看板が立ち並び、
西陣織を支える分業制が街の隅々まで浸透していることを感じていただけるでしょう。
怖くない産地見学会をお約束します
昔々に呉服屋さん主催の産地見学会などに参加したことがある方からは、
現地で購入を強く勧められて怖かったなど、少なからず心配されるお声を聞くこともございます。
昔はそういうこと結構ありましたよね…。
今回開催にあたって、訪問する企業様すべてに
このような販売会を主としたツアーではないことを理解していただいております。
純粋に、まずは西陣織の魅力を知っていただきたいというのが主催側および受け入れてくださる企業様の願いです。
ですので、皆さまの前には高級懐石ランチも音楽演奏も舞妓さんも出てきません(笑)
午前中は西陣の街を歩きながら、織の工房を見学します。
お昼は、産地問屋さんの社屋の一室を借りて、
西陣OL達に愛される地元ローカルのお店にオーダーしたお弁当をカジュアルにいただきます。
午後はリユース着物目利き講座の原清華先生による西陣織の講座です。

講座の後は時間を決めて自由に産地問屋さんの商品を見て、触らせていただきます。
商品を見るだけでなく、産地問屋のスタッフさんとお話するというのも良い経験となるかと思います。
もちろん欲しいと感じたものがあれば購入することができます。
お値段は先ほど冒頭でお伝えしました通り、西陣織には超お高級なものもプチプラ優秀品も幅広くございます。
「何かいいものがあったら欲しいな」とほんのり期待して来ていただくのはもちろん、
絶対買わないぞ!と心を鬼にして来ていただいてもOKです(笑)
今までリユース着物目利き講座で、原先生のことを知っていただいている方々には無用の説明かもしれませんが、
どうぞ自由な気持ちで安心して参加してください。
さいごに
西陣はバリエーション豊かな商品を生み出す巨大産地。
この多様性のなかに着物初心者が放り込まれる経験ほど勉強になることはないでしょう。
着物に詳しくなりたい、もっと身近に着物を感じたい、そんな方は是非このツアーにご参加ください。

募集概要
リユース着物目利き講座の原先生と産地を巡る見学&勉強会。
カジュアルからフォーマルまで、着物ファン信頼の巨大産地 西陣の歴史と最先端の製造現場でその技術を学びます。
イベント名
はこにわリユース着物目利き講座presents
産地を読み解く勉強会 西陣織工房見学編
開催日
2022年11月11日(金)
10:00〜16:00(うち1時間お昼休憩)
講師
原 清華先生(京都の着付け教室 きものシャン)
参加費
お一人 8,000円(税込) 昼食代(お弁当)込
※苦手な食材やアレルギーについてはお申し込み時の備考欄にてお知らせください
お支払いについて
ゆうちょ事前振り込み
お申し込み後、メールにて振込先をご案内いたします。
1週間以内にお振込みをお願いします。
お振込みをもってお申込み完了となります。 振込先、入金期限を必ずご確認ください。
定員
8名 先着順
会場
集合場所 西陣織会館
京都市上京区堀川通今出川南入西側
→アクセス
・市バス
最寄バス停「堀川今出川」下車 徒歩1~2分
京都駅より=9番 約30分 ・ 101番 約20分
四条河原町・四条烏丸より=12番 約20分
四条大宮より=201番 約15分
三条京阪より=12番・59番 約25分
京阪出町柳より=201番・203番 約15分
・タクシー
京都駅より約20分
・地下鉄
烏丸線「今出川」駅下車 徒歩約10分
解散場所 帯みのり
京都市上京区元誓願寺通智恵光院西入元中之町515
お持ち物
- 筆記用具(鉛筆またはシャープペン ボールペンは不可)
- スマホ、カメラ付き携帯電話、タブレットで写真撮影可能。
録音、動画撮影は禁止します
服装
お洋服でもお着物でもお気軽にご参加ください。
機織りの工場など汚れやすい場所に入ることもございますので、
お召しになるものには十分にご注意ください。
汚損の場合、主催者は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
お申し込み方法
10月10日(月)19:00より受付開始 先着順
※複数人でご参加の場合はお一人ずつお申し込みください。
※10月10日(月)19:00以前は上記のボタンは機能しませんのでご注意ください。
お申し込み締め切り
11月4日(金)23:59
お弁当の手配があるため、イベント1週間前までの締め切りとさせていただきます
注意事項
- マスクを必ずご着用ください。
- 体調にご不安がある方、当日の体温が37.5度以上の方のご参加はお控えください。
- 社会情勢によりイベントは中止・延期になる可能性もございます。主催者からの案内を必ずご確認ください。
- 記録のために写真や動画を撮影することがあります。集合写真も撮影しますので、顔出しNGの方は事前にお知らせください。当日の申告でも大丈夫です。
- 着物業者様および着付け講師先生方におきましては、講座への参加をご遠慮いただいております。
キャンセルについて
- ご入金後の返金は致しかねます。ご自身のスケジュールをご確認の上お申し込みください。
- キャンセルは必ずご連絡ください。無断キャンセルはご遠慮願います。
主催
- 帯みのり
- 京都の着付け教室 きものシャン
- 和と人を結ぶイベント はこにわ
お問い合わせ
全てのお問い合わせははこにわ事務局へお願いします。
→お問い合わせフォーム
当日のスケジュール
2022年11月11日(金)10:00〜16:00
タイムテーブル
| 10:00 | 集合 |
|---|---|
| 10:00〜10:30 | 西陣織会館クイックツアー |
| 10:30〜12:00 | 工房見学(西陣まいづる様・手機&織機/都様・すくい織) |
| 12:00〜13:30 | 休憩(産地問屋社屋にてお弁当) |
| 13:30〜14:30 | 産地問屋で学ぶ西陣史&西陣織のバリエーション講座 |
| 14:30〜16:00 | 触れて楽しむ西陣織タイム |
| 16:00 | 終了(最寄り駅までタクシーの手配などご案内いたします) |
3会場間は全て徒歩で移動します。
それぞれ5〜10分程度です。
お申し込み方法
10月10日(月)19:00〜 受付開始
専用のフォームからお願いします。
お申し込み後、メールにて振込先をご案内いたします。
1週間以内にお振込みをお願いします。
お振込みをもってお申込み完了となります。 振込先、入金期限を必ずご確認ください。
受講までの流れ
お申し込みフォーム送信
↓
(メール1通目)自動返信メール
↓
(メール2通目)お席確保のご連絡、ご入金先のご案内
↓
ご入金
↓
(メール3通目)入金確認連絡
↓
受付完了
↓
(メール4通目)事前資料送付
当日の見学がより楽しめるように、事前に資料や動画のリンクをお送りします。
各自お時間のある時に予習をお願いします
↓
当日
メールが届かない場合は迷惑メールに振り分けられているか、
なんらかのエラーでメールが送れていない可能性があります。
お手数ですが再度お申し込みいただくか、はこにわ事務局までご連絡ください。
全てのお問い合わせははこにわ事務局様へお願いします。