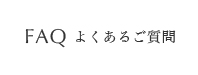西陣紀行 cafe marble🕊 カフェ マーブル☕️智恵光院店
2022.10.27

(画像は2022年6月帯みのり撮影 )
みなさま、こんにちは🌈
いつも帯みのりのblogをご覧下さりまして
誠にありがとうございます🙏🏻
今日は西陣のオシャレcafe
「cafe marble カフェ マーブル 智恵光院店」のご紹介をさせて頂きます☺️
カフェ マーブルがあるのは、
西陣エリアだけあって
織物や着物に関連するものを商う会社がにぎわう京都市上京区です。
4階建ての昭和モダンなビルの1階、2階で、
壁面いっぱいに大きな窓があります✨
窓の外は、
休日となれば家族連れでにぎわう大きな橘公園🌲🌲🌲
窓辺で座っていると、
子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきます🕊
2階が利用できるのは、現在は土曜日🐈
不定期で平日にもあけていることがあるそうです。
1階は、コンクリート打ち放しで、
オープンキッチンに面したカウンター席とテーブル席があります✨
ウッドフロアの2階は、1階よりも広々とした空間で、
テーブル同士のあいだも
ゆったりとスペースがとられています。
デザイナーズカフェというだけあって、
壁のちょっとした手描きのイラストから、メニュー、
置物に至るまで全てに統一感があり、
眺めているだけでとっても楽しくなります。
そして、なんと😳
cafeの前には駐車スペースが4台分あります🚙
京都市内のカフェではかなりレアです✨✨✨
お子様連れのママさんや
少し遠方からお越しの方にはかなり助かります。

(画像は2022年6月帯みのり撮影 )
フードメニューに
スイーツを追加すると100円引き、
プラス200円で
ドリンク(コーヒー、紅茶、ジュース)
付きになります🍰🥤☕️🍹🫖
キッシュは、
自家製のサクサクの濃厚なパイがとっても美味しく、
中のキッシュ部分も色んな野菜が入っていて
味の変化がとても楽しい一品です🥧💕

(画像は2022年6月帯みのり撮影 )
以前、私が頂いたのは、
サンドウィッチのセットです。
ふわふわのやわらかい食パンの中に
クリームチーズとパストラミビーフ、
くるみ、グリーンリーフが挟んでありました。
サンドウィッチにくるみ???
って一瞬思ったのですが、
クリームチーズとくるみが合わさると、
濃厚なスイーツのような味わいになって、
めちゃくちゃ美味しかったです😂💕
あの感動以来、
我が家にはクリームチーズとくるみを切らさないように備蓄しております。
プチメックやエズブルーの
とびっきりの美味しいパンを買って来ては、
挟んで食べるのにハマっています。
個人的には、プチメックのチャバタに、
クリームチーズとくるみを挟むのがかなりのオススメです。
ハムは生ハムでも物凄く美味しかったです。
(えっと、、、料理blog?)

(画像は2022年6月帯みのり撮影 )
食後にピスタチオのタルトを頂きました💕
これまたサクサクのタルト生地に、
濃厚なピスタチオのフィリングが
ものすごく美味しくて、
一緒に添えられたバニラアイスとピスタチオクリームと一緒に食べると
本当に美味しかったです😂💕
最近、チョコやアイスなど
ピスタチオブームですが、当たり外れも多くて💦
しかしながら、
こちらのスイーツは納得の美味しさで
大満足の一品でした👍👍👍

(画像は2022年6月帯みのり撮影 model Yumiko.H )
2階は、デザイナーズカフェだけあって、
こだわりのインテリアがいっぱい⚡️⚡️⚡️
インテリア好きといたしましては、
大興奮を押し殺すことができず、
シャッターが止まりません✨✨✨✨✨

(画像は2022年6月帯みのり撮影 model Yumiko.H )
一つ一つの小物から、
壁にサラッと書いてあるイラストまで、
とてつもなくセンスが溢れています✨✨✨
まさに、アートギャラリーカフェ!!!

(画像は2022年6月帯みのり撮影 )
明るい窓の隣に設けられた
キッズスペースは
インスタ映え間違いなしの超絶オシャレ空間🕊🕊🕊
モロッコのプフも普通の生地じゃございません。
ホワイトの毛糸です!最先端!!!
無造作に置かれた積み木もオシャレだけじゃなく、
知育としてもハイレベル!
少し前までは、子供用テントが物凄く流行ってましたが
ここ最近はこういったホワイトのティピーが主流ですよね。
親子で、友達で、ひとりで、
どんなシーンでも楽しめる
西陣のおしゃれカフェです⭐️⭐️⭐️
カフェマーブル智恵光院店
https://www.cafe-marble.com/shop/chiekoin/
#京都 #西陣 #帯みのり

帯みのり